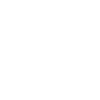太宰府と大伴旅人
神亀(七二七)、奈良の都より太宰府へ着任した太宰師大伴旅人の目の前に、若くて美しい都城の条坊が広がっていた。それは、まさしく、「天皇の遠の朝廷」と称するにふさわしい古代都市の威容だった。旅人は、天智天皇四年(六六五)、大納言大伴安麻呂の長男として生まれた。
左将軍、中務卿、中納言、征隼人特節大将軍を歴任し、六三歳という高齢をもって、太宰師に任命された。妻の大伴郎女、長男の家持ちの子供に、一族家人を伴っての大転勤である。
この時、太宰府には、小野老が太宰小弐、山上憶良が筑前守、そして沙弥満誓が造観世音寺別当として赴任していた。そこに、旅人を迎えることによって、太宰府に後世、筑紫花壇と表されるほどの華やかな万葉の文化が華開いたのである。
筑紫路文学は、ここに始まった。しかし、旅人は着任後間もなく、最愛の妻郎女を病気で失った。
また、一方、都では、天兵元年(七二九)、左大臣の職にあって、藤原氏の勢力を抑えていた長屋王が、謀反の疑いをかけられ自殺させられるという事件が起き、続いて藤原不比等の娘が、天皇の皇后に初めてなった。これらの事件は、藤原氏による政権の独占を意味する反面、大伴氏などの古い豪族の没落を誰もが感じていた。
実は、旅人が太宰府へとうざけられたのも 藤原氏の計略のひとつだった。
しかし、この太宰府は都に対し、「天ざかる鄙」という自らの立場を一貫させていたのである。
旅人は、庭に梅を植え、それを詠じるという中国の文化をいち早く取り入れた。天平二年正月十三日に旅人の館で開かれた梅花の宴には三三人の官人が招かれた。
「わが苑に梅の花散るひさかたの天より雪の流れくるかも」 そして、次田の湯では、
「湯の原に 鳴く蘆鶴は 我がごとく 妹に恋ふれや 時わかず鳴く」とひとり歌っている。
天平二年一二月、大納言に任せられた旅人が都へ帰ることとなった。一世を風靡した筑紫花壇も三年で幕を閉じた。あれほど望郷の思いに駆り立てられた旅人もいざというと、太宰府を去り難く、別れにあたって、涙する。見送る人々の中には遊女児島の姿もあった。
「丈夫と思へるわれや 水茎の 水城の上に 涙拭くなむ」
万葉集二〇巻の編者として、日本文化史上に不朽の業績を残した人である。